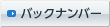130:5 私は主を待ち望みます。私のたましいは、待ち望みます。私は主のみことばを待ちます。
130:6 私のたましいは、夜回りが夜明けを待つのにまさり、まことに、夜回りが夜明けを待つのにまさって、主を待ちます。
この詩篇の著者は、「深い淵」の中で主を呼び求めます。そして、そこで主があわれみ深いことを発見し、主に救いを求める人を拒絶されないことを体験します。
彼が次にすることは、主を待つということです。
二つ目の段落をまとめる動詞は「待つ」という言葉です。神を「待つ」ことは簡単ではありません。特に自分が溺れそうである、また窒息しそうな精神状態に陥っている場合は特にそうです。しかし、そこを通ることが希望につながる唯一の道であり、あわれみ深い主の働きを体験できる手段なのです。
著者は、「私のたましい」は待つと言います。ここで「たましい」と訳される「ネフェシュ」という言葉は、人間の「喉」、「首」、「息」などを指すことに使われますが、文脈によっては人間の目に見えない本質、つまり人間の「意識」や「理性」や「感情」などをすべてひっくるめたものを指す時に使われます。つまり、著者の内側のすべてが主に期待をし、いつでも行動を起こしてくれることを待ち望んでいるさまが書かれています。
しかし、主を待つとは、何もせず、ただ運命に身を任せることと異なります。著者は、主を待つのと同時に積極的に「主のみことばを待ちます」と言います。ここで使われる「待つ」と訳されている言葉は、同じ節で「待ち望みます」と訳されている言葉とは異なります。ここで使われる言葉は、「信頼する」、または「期待する」というニュアンスがあります。ですから、神の救いを待つ人の姿は、神の約束を心に豊かに蓄え、しっかりとそれに希望をおいて、不信な心が生まれないようにしている姿です。

「深い淵」に落ちた経験のある人は誰でも、主の言葉だけに確信を持ってゆだねることが簡単ではないことを知っています。しかし、それ以外の手段で脱出を試みると、一つの問題を解決するために、さらに複数の問題を作ってしまうパターンが生じます。
6節では、主の約束に信頼する著者の待ち遠しさがさらに強調されます。日本語訳では、「私のたましいは、夜回りが夜明けを待つのにまさり、まことに、夜回りが夜明けを待つのにまさって、主を待ちます」と訳されていますが、実際の原文では「私のたましいは主を...夜回りが朝を...よりも、まさに夜回りが朝を...よりも」というように不完全な文で書かれています。
これも昔の詩的表現で、あえて大切な言葉や動詞を意図的に文章から外すことによって読者たちがそこで強調したい言葉に心を留めるようにしたのです。もちろん、文脈からここで抜けている言葉は「待つ」であることが分かります。そのため、「待つ」ことの大切さに、さらに焦点を絞ることができたのです。
130:7 イスラエルよ。主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。
130:8 主は、すべての不義からイスラエルを贖い出される。
最後の段落をまとめる動詞は、「希望を持つ」という言葉です。新改訳聖書では「待て」と訳されていますから、5節の「待ち望む」という動詞との意味的な区別がつきません。しかし、ここで使われている動詞は、5節の後半で、「主のみことばに確信する」と書かれている言葉と同じ言葉です。
これまでは、著者が一人称単数系(「私は...」)を使って「深い淵」から救出を望んでいました。しかし、この段落では名詞が三人称(「イスラエルよ」)に変わっています。
著者は、主のことばに信仰を持ったことによって、希望が与えられたのです。この詩篇の最後の数節が執筆された時点で著者が「深い淵」から脱出できていたのかは記されていません。ひょっとすると、まだ淵の中からこの詩篇の最後の言葉を書いたのかもしれません。しかし、それがどこからだったのかは今では関係ありません。著者の体験と確信が、罪によって「深い淵」に置かれていたすべてのイスラエルの民に同じ希望を与えることができることを彼は悟ったのです。
この著者の希望は、精神論や根性論によって生まれたのではありません。または、時間や環境の変化に任せたものでもありません。この希望は「主」にあるのです。
なぜ著者が主に希望を持てるのかというと、それは、主が愛であり、私たちを救う力を持っておられる方であるという現実があるからです。
主には、「恵み」があると書かれています。ここで「恵み」と訳されている言葉は、「ヘセッド」という言葉で、神がイスラエルの民に特別に示された愛情を指す時に使う言葉です。神がモーセを通して与えた契約に忠実でいてくださること、そして、アブラハムと結んだ契約に基づいて祝福してくださると約束された、神の変わらない一方的な誠実さを表します。

そして、著者は主には「豊かな贖いがある」ことを発見しました。ここで「豊かな」と訳されている言葉は、あふれ続ける、蓋をすることができない状態のものを指すときに使われます。また、「贖い」とは神の救いの力を指します。苦しみの状態から解放する神の力が神の贖いの力です。
神が状況を変えてくださらないのは、力はあるが愛がない、または愛はあるが力がないからではありません。まことの主には両方が備わっており、必ず神の計画の中で私たちに最善のタイミングで私たちを救出されるのです。それらのことを理解した著者は、そのような神の性質に希望をおくように命じたのです。
著者はこの詩編を締めくくる言葉として、「主は、すべての不義からイスラエルを贖い出される」と言いました。このような終わり方は、「私を救い出してください」と願っていた初めの内容と無関係な印象を受けるかもしれません。
しかし、この締めくくり方は、この詩篇が「都上り」の歌であるため、その目的に相応しく書かれているのです。詩篇の著者は、自分の信仰の旅の中で、絶望から希望に導いてくださる神を再発見しました。これまでのたった7節だけで、神の聖さ、赦し、正しい恐れ、約束に対する誠実さ、ご自身の民に対する愛と救いの力についての発見を書き記しました。そして、著者は、それらの真理が自分だけに当てはまるものではなく、主を礼拝するためにエルサレムに上るすべての民に当てはまることを伝えたかったのでしょう。
そして、イスラエルの民のすべての不義から彼らを必ず贖うことができる神がおられるのであれば、その同じ神が自分をどのような「深い淵」からでも救うことができるであろうと考えるのです。
この詩篇から学ぶ事
この詩篇は、イスラエルの民だけにではなく、すべてのクリスチャンに多くの大切なことを教えます。
まず、神に属している人であったとしても人生のどん底に突き落とされることがあるということです。神を信じれば、人生がばら色になり、病が治り、金銭に恵まれ、すべてが祝福に変わるという考えは悪魔の罠です。
この詩篇の著者は、「深い淵」にいました。それは彼が罪を犯した結果であったかもしれません。理由は、何であったとしても神に属する人が苦しみを体験しなくなるということは聖書のどこにも書かれていません。
かえって、ヨブや福音のために殉教していったパウロを代表とした弟子たちの人生を振り返る時、義人であったとしても苦しむことがある、いや、義人だからこそ特別に苦しむことを学びます。
「確かに、キリスト・イエスにあって敬虔に生きようと願う者はみな、迫害を受けます。(IIテモテ3:12)」と聖書は教えます。しかし、愛であり、知恵のある神は、意味なく私たちを苦しめることはありません。かえって、それを用いて、その人がさらに神に用いられる器となるように働いてくださっているのです。「苦しみに会ったことは、私にとってしあわせでした。私はそれであなたのおきてを学びました(詩篇119:71 )」とダビデは歌いました。
人間としてこの罪によって堕落した世界に住んでいる間は、義人も罪人も苦しみを体験します。しかし、その背後には、私たちを赦し、救うタイミングを待たれている愛と力の主がおられるのです。
また、もう一つの大切なこととして、聖書が求める信仰は、信じる量よりも信じる信仰の対象の方が大切であることを教えています。私たちが間違った情報を一生懸命信じたとしても、それによって世界が変わるわけではありません。
日本人は精神論や根性論が比較的好きな民族ではないでしょうか。信じることに意義がある、また信じることによって何でも乗り越えることができる、と感じやすいですが、聖書が教える信仰に関して言えばそのような考え方は通用しません。
なぜなら、世界は私たちを中心に動いていないからです。世界は、それを創造された神を中心に動いており、神の御心が前進するように計画されているのです。

聖書は、信じる対象が神によって約束されていれば、それがどれほど私たちにとって実現不可能なように思えたとしても、「からし種」ほどの信仰で神がそれを実現させてくれることを教えます。しかし、私たちの信仰が神の約束ではなく、信じる力に頼っているのであらば、山のような信仰を持ったとしてもからし種ほどの問題も解決することができません。自らの信仰の力に信仰を持つのではなく、主のことばに信仰を持つことによって初めて神の救いに希望を置けるのです。
これ以外にも多くの学ぶことがありますが、それは別の時に、別の場所でさせていただきます。
今回の投稿でこのシリーズの連載はひとまずお休みにさせていただきます。このシリーズを通して、聖書を学ぶ奥深さ、また真理に出会う喜びを体験していただけたというのであれば、とても感謝です。